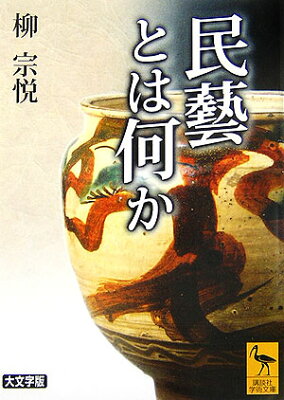<番組紹介>
焼き物の生産が盛んな鳥取県。
民芸運動の拠点のひとつで、
現代の生活に合うモダンな器作りの伝統が作られた。
現代の職人たちも、丈夫で、使いやすく、
彩り鮮やかな器作りに取り組んでいる。
軽いが丈夫なティーポット、
明るい緑色が印象的な3色染め分け皿、
そして独自の技法で 星座の模様がちりばめられたカップ。
それぞれの窯元を訪ね、
手間ひまかけた丁寧な手仕事を紹介する。
リポーターはモデルの生方ななえさん。
<初回放送:令和3(2021)年2月21日>
鳥取県と言えば、「鳥取砂丘」を思いがちですが、
実は、焼き物の生産も盛んなところです。
鳥取県は土や石の種類が豊富であったことから、
江戸時代より焼き物づくりが盛んに行われていました。
そして昭和6(1931)年頃から、
鳥取県に民藝運動を広めた吉田璋也(よしだ しょうや)により、
鳥取の伝統的な焼き物は、モダンな雰囲気の焼き物へと
生まれ変わりました。
現在、鳥取県にはおよそ30もの窯元が点在しています。
これらの窯元では、吉田の精神を引き継ぎ、
独自のスタイルで、生活に根差した作品を作り続けています。
近年、これらの作品は若い世代からも評価を受け、
とても人気があります。
1.福光焼(河本賢治さん・慶さん)
「福光焼」(ふくみつやき)の工房は倉吉市福光にあります。
初代の河本賢治(かわもと けんじ)さんは15歳で陶工の道を志し、
民藝運動の推進者・河井寛次郎氏を師とした
生田和孝(いくた かずたか)氏のもと、丹波で修行を積み、
昭和55(1980)年、故郷の倉吉市福光に登り窯を築炉して、
独立しました。
現在は、息子の慶さんと共に作陶されています。
河本賢治さんは、師匠の生田和孝が得意とした
「面取」(めんとり)や「鎬」(しのぎ)の造形技術を継承し、
伝統技法の「蹴りろくろ」や「登り窯」という方法を守り
作陶を続けています。
釉薬は糠白、飴、鉄が基本。
白と黒を基調とした「面取り」が施されたモダンな器は
シンプルながらも凛とした存在感を感じさせます。
番組では、とても軽いのに丈夫なティーポットの
制作模様が紹介されました。
まず、自らの足で蹴って回す「蹴りろくろ」を使って
ポットの形を作っていきます。
現在は、「電動ろくろ」が主流ですが、
「蹴ろくろ」のリズムの違いなどによって生まれる
個性を大切にしているのです。
作業を初めて3分で形が完成。
注ぎ口、蓋を作り、パーツが揃ったところで
軽くするために余分な側面を削る「面取り」を行います。
一見簡単そうに見えるのですが、
河本さんはポットの膨らみに合わせて削る角度を変え、
更に、刃を下す時に右側に滑らすようにして削っていきます。
こうして出来上がった器は、一つ一つ少しずつ姿が異なっています。
また、ろくろで挽いた時についた指の跡もうっすらと残っています。
河本さんの焼き物に「登り窯」は欠かせません。
「登り窯」は丘などの傾斜面に建っています。
内部は階段状にいくつかの小部屋に分かれていて、
一番下が「大口」と呼ばれる燃焼室(窯口)で、
上に沿って部屋が続き、
最上部の部屋の先には煙道、そして煙突へと続いています。
各室の天井はかまぼこ形をしていて、
部屋の前部の床にはいくつかの穴が開けられ、
後部の壁には下の窯から焚き出した火が登っていくように穴が開いています。
炎が低いところから高いところへ流れる原理を利用し、
「大口」の燃焼の余熱を各室に利用して焼成していきます。
単一の大きな窯の場合は、窯内は熱が均等に行き渡らないため、
場所によって温度にムラが出てしまいますが、
「登り窯」の場合は、それぞれの小部屋で循環するので
一定の温度で、全ての器を同じように焼くことが出来ます。
但し、窯の温度管理は難しいです。
目標とする温度は1250度。
薪を少しつ投入して、じわじわと上げていきます。
上げ過ぎると器が割れてしまうため、一瞬の気の緩みも許されません。
この作業が28時間つきっきりで行われます。
完成したポットは焼く前に比べて2割収縮しますが、
その分丈夫になっています。
一旦焼き物にした土は戻せないので、
最後までいい姿にしてやりたいとおっしゃっていました。
今日の午前中に倉吉の福光焼窯元に仕入に行ってきました。今回はカップ類を中心に色々と選ばせて頂きました。先程店頭に全て並べましたのでご興味のある方は是非! pic.twitter.com/iv9sv9uBBu
— 器屋うらの (@utsuwayaurano) March 22, 2022
福光焼
- 住所:鳥取県倉吉市福光800-1
- 電話:0858-28-0605
2.「三色染分皿」(因州中井窯・坂本章さん)
吉田璋也(よしだしょうや)は、
新潟医学専門学校在学中に文芸雑誌『白樺』の影響を受け、
後に民藝運動の父と呼ばれる柳宗悦に師事するようになりました。
帰郷した吉田は、昭和6(1931)年に
「牛ノ戸焼」(うしのとやき)の
「五郎八茶碗」(ごろはちぢゃわん)に出会い、
四代目・窯元の小林秀晴を説得して、新作民藝運動を始めました。
その代表作は、二色に染め分けた「染分皿」です。
「牛ノ戸焼」の小林は吉田璋也の指導を受けて、
右側がそれまで黄土色だったものを緑にした、
緑と黒の「染分皿」を最初に作り出しました。
「中井窯」は、その「牛ノ戸窯」の脇窯として
昭和20(1945)年に鳥取県河原町に開窯した工房です。
二代目の坂本實男は吉田璋也の指導を受け、新作民藝に取り組みました。
そして現在の当主である3代目の坂本章さんも吉田の思いを受け継ぎ、
更には「もやい工芸」の故・久野恵一さんとの出会いによって、
作陶をしています。
章さんの作る「染分皿」は、
染め分けの特徴でもあった吉田が生み出した「緑」を
モダンで明るくやわらかな緑へと更に進化させることで
緑・白・黒の三色を力強く対比させた「三色染分皿」です。
鳥取を代表する民藝品。独特な色合いが美しい【因州・中井窯】の器https://t.co/uBhaKvTiDJ pic.twitter.com/6dvFaZiRIn
— キナリノ公式 (@kinarino) November 15, 2016
平成12(2000)年からは、民藝の生みの親である柳宗悦の息子で
工業デザイナーの柳宗理さんの「柳ディレクション」シリーズも
作陶しています。
それだけでなく、
「青瓷」(せいじ)という新たなフィールドにも挑戦しています。
平成30(2018)年からは四代目の宗之さんも加わり、作陶しています。
「染分皿」はまず、お椀の形にしてから。
製図用の定規を使って
普通、手作りで作った皿は表面の凹凸を大切にしますが、
章さんは滑らかに仕上げます。
この皿の主役はあくまでも「色」。
他の要素は敢えて切り捨てているのです。
下地には白い泥を塗って、
上に塗る釉薬の色を明るく見えるようにします。
釉薬は黒、白、緑の三色。
特に「緑」の釉薬にはこだわりがあります。
通常「緑」の釉薬は、
「木の灰(木炭)」と「長石」に「酸化銅」を加えて作ります。
章さんは、緑色をより明るくするために
「木炭」の代わりに「藁灰」という白く発色する素材を使います。
まずワラを燃やして出来た灰を水に浸けます。
するとその「藁灰」についていた不純物が水面に浮かんでくるので、
一旦、その水を捨て、再び水を入れて
浮いてきた不純物を取り除くという作業を何度も繰り返します。
「藁灰」と「木炭」を比べると、
「木炭」はすぐに沈殿していきますが、
「藁灰」は軽いので変化がありません。
作業そのものは単純なのですが、時間が掛かります。
坂本さんがつくる「藁灰」は、一回沈殿するのに三ヶ月掛かり、
それを何回も繰り返すために一年の月日が掛かるそうです。
いよいよ釉薬を入れていきます。
まずは黒を付け、次に白を付け、最後に緑を付けます。
この後窯で12時間焼いたら完成です。
伝統を受け継ぎながらも、新たな境地を目指した一品となっています。
鳥取の自然と文化を取り入れた
「中井窯」が手掛けています。
鳥取市の新市庁舎、地元産品にこだわった作りでした。トイレの洗面台は因州中井窯、西郷地区にある窯元の1つです。実は、JRのスーパーはくとでも使われていました(こっちは写真が暗くなってしまった💦) pic.twitter.com/6bNN4Tn6X3
— 山川良子(地域おこし協力隊@鳥取市河原町西郷地区) (@rsrt815) February 16, 2020
- 住所:鳥取市河原町中井243-5
- 電話:0858-85-0239
3.「線文」(国造焼・山本佳靖さん)
「国造焼」(こくぞうやき)は、明治23(1890)年に創業した
鳥取県倉吉市不入岡(ふにおか)にある窯元です。
近所にある「こくぞうさん」と呼び親しまれた
「伯耆国造」(ほうきのみやつこ)を祀った大将塚にあやかって
昭和50(1975)年、初代・秀治さんが創始しました。
山本佳靖さんは、国造焼の4代目。
3代目の父の背中を追いかけ陶芸の世界に飛び込んだのが20歳の時。
伝統の技を磨きつつ、新たな作品作りにもチャレンジしています。
現在は、妹の花野子さんも創作活動に参加。
淡いブルーが美しいこちらの器は、家族で工房を構える国造焼(こくぞうやき)の山本花野子さんの作品。JR鳥取駅にほど近い「gallery shop SORA」で出会えますよ。https://t.co/mcIffjvGtl pic.twitter.com/hsUQtHPnCX
— ことりっぷ (@cotrip_twi) March 12, 2022
現在、四代目の山本佳靖さんが作陶する器は
シンプルで洗練されたデザインが印象的。
中でも、「線文マグカップ」は、
深い茶色の小さな三角形を極細の線で繋いだ独特の文様に
目を奪われるマグカップです。
隣り合った三角形はリボンのようにも見え、
線で繋がった形は、まるで星座のようです。
使うのは、先祖代々大事にしてきた赤土を溶いた泥です。
山本さんの御先祖は、
不入岡(ふにおか)の土が焼き物に適していることに着目して、
この地に移り住み、代々土を大切にしてきました。
マグカップを作ったら、
まず鉄分を含んだ不入岡の赤い土を化粧土として塗ります。
僅かな量でも発色が良くなるので、薄く吹き付けます。
素焼きしたら、白い釉薬を掛けます。
国造焼の白釉の白色は
注がれた飲み物や盛り付けられた食材がより美しくキレイに見えるように
努力を重ねて生まれた白色です。
白い釉薬が乾いたら、「ケガキ針」という鉄の棒で
星座のような模様に掻き落としていきます。
「線文」は失敗から生まれたものだそうです。
ある日誤ってカップの表面を鉄の棒で引っ掻いてしまい、
試しにそれを焼いたところ、赤い下地が見え面白いと感じ、
これを活かしたいと思いました。
そこからが試行錯誤。
最初は絵心一杯のものを作ってみましたが
これでは万人受けするのは難しいと考え、
そこでランダムに線を引いてみたもののそれには納得出来ず、
遂に辿り着いたのが星座のデザインでした。
失敗の中にヒントを見出す、職人の逞しさが生んだイッピンです。
国造焼さんの新作、角皿に続き、人気の線文のカップ&ソーサーやケーキ皿が登場です!花のような、星座のような幾何学文様が、気分も美味しさも盛り立てます。カップは口当たり良く、持ちやすく飲みやすいフォルム!
— SHIMATORI 米子店 (@shimatori_net) July 15, 2020
詳しくはオンラインショップページへどうぞ★https://t.co/184CMJK2B7 pic.twitter.com/X4gtoKQgJZ
国造焼
- 住所:鳥取県倉吉市不入岡390
- 電話:0858-22-8388